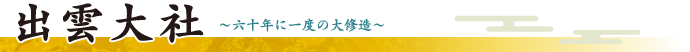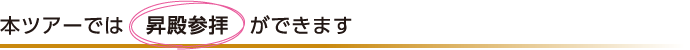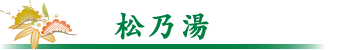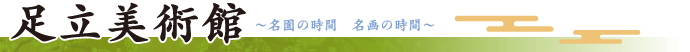三交旅行総合トップ > 三交パルックトップ > 出雲大社昇殿参拝と美肌姫神の湯玉造温泉


出雲大社は、大國主大神(おおくにぬしのおおかみ)を御祭神としてお祀りするお社です。国宝に指定されている現在の御本殿は、高さが8丈(約24メートル)あり、延享元年(1744)の造営以来、文化6年(1809)、明治14年(1881)、昭和28年(1953)と3度の御修造が行われてきました。そして、平成20年から、60年ぶりの御本殿他諸社殿等の御修造「平成の大遷宮」が進められています。「御遷宮」とは神社本殿の御造営・御修造による宮遷しのお祭です。この度の御遷宮では、平成20年4月20日に、大國主大神さまを仮のお住まいの御仮殿(従来の拝殿)へお遷りいただく「仮殿遷座祭」が斎行されました。その後、5年にわたる御本殿他諸社殿等の御修造を経て、平成25年5月10日、大國主大神さまが元の御本殿にお遷りになる「本殿遷座祭」が執り行われました。
本ツアーでは御遷宮が行われた出雲大社で昇殿参拝を行います。出雲大社での昇殿参拝は、神楽殿または仮拝殿に昇殿していただき、団体祈祷を受け、バス1台につき1名の代表の方に玉串拝礼を行っていただきます。時間にして20分程度ですが、通常の参拝とは違うより神聖な時をお過ごしいただけます。また、一人ひとり肌守りを授与していただきます。

出雲大社の神殿成立の記録上の初見は、斉明天皇5年(659)に「厳神之宮」として神殿を修したことが見えます。以後、幾度にも及ぶ御修造が行われ、当時も賑わいを見せていたと文献により伝えられています。

「平成の大遷宮は」平成20年4月から平成28年3月までの8年間に渡る御修造です。この度の御遷宮では、御本殿は建て替えられず、主に大屋根の檜皮の全面葺き替えや、風雨などで腐朽した部材の修理が行われます。

この湯につかればつかるほど姫神のように麗しき肌となる。玉造の湯は美肌の湯と名が広まり「姫神の湯」と呼ばれるようになりました。平安時代には「玉造」の名は京の都まで届き、貴族の間でも評判になっていたと清少納言は「枕草子」で触れています。硫酸塩泉と塩化物泉が絶妙にブレンドされたお肌にやさしい弱アルカリ性でお肌にハリとスベスベ美肌効果が期待できます。
-
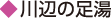
まがたま橋のすぐ横、玉造温泉の中心を流れる玉湯川河原にあり、温泉街をぶらっと散策がてら、疲れた足を癒すのにピッタリのポイントとして人気を集めています。

-
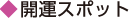
まがたま橋から玉湯川上流を見るとまがたまの形をした小島がある。島の真ん中には「青めのう原石」があり、これに触れると幸せが訪れると言われています。

-
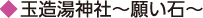
玉造湯神社には、その昔村人の願いを叶えてきたと言う「願い石」があります。その不思議なパワーを宿す「願い石」は日本随一のパワーストーンとして注目を集めています。

玉造温泉街のほぼ中心に位置する旅館です。当館の前身である料亭・松崎水亭以来100年の伝統を生かした料理と、「湯・遊・悠のおもてなし」の心でお待ち致しております。日本庭園の情緒と、吹き抜けの開放感溢れる湯殿が自慢の大浴場「月照の湯」、露天・ジャグジー・サウナ等を完備し、疲れを癒す空間となっております。趣異なる4種類(木・石・陶器・瓶)の貸し切り露天風呂はご家族連れのお客様にご好評です。
日本松と曲水が映える『曲水の庭』をはじめ、自然美豊かな『和(なごみ)』が魅力の宿。 夕暮れには篝火(かがりび)も焚き、さらに癒しのひと時を演出します。また、夜9時10分からはロビーにてプロによる『安来節ショー』も上演しており、目の前の浮き舞台で上演される『どうじょう掬いおどり』は好評です。当地最大を誇る大浴場は、一度に200名の同時入浴も可能です。巌の迫力と、檜の薫りが楽しめる2つの大浴場は、朝夕男女入替なので朝晩の入浴で両方楽しむこともできます。

日本庭園の美しさでも知られる足立美術館。創設者足立全康は庭園をこよなく愛し、91歳で亡くなるまで、自分の目と足で全国から植栽の松や石を蒐集し、庭造りに情熱を傾けました。枯山水庭をはじめ、50,000坪におよぶ6つの庭園は、四季折々にさまざまな表情を醸出します。自然と人工の調和美をご覧ください。

| 1位 | 足立美術館(島根県) | 6位 | 栗林公園(香川県) |
|---|---|---|---|
| 2位 | 桂離宮(京都府) | 7位 | 養浩館(福井県) |
| 3位 | 常磐ホテル(山梨県) | 8位 | 無鄰菴(京都府) |
| 4位 | 平安会館(京都府) | 9位 | 佳翠苑 皆美(島根県) |
| 5位 | 山本亭(東京都) | 10位 | 石亭/庭園の宿(広島県) |